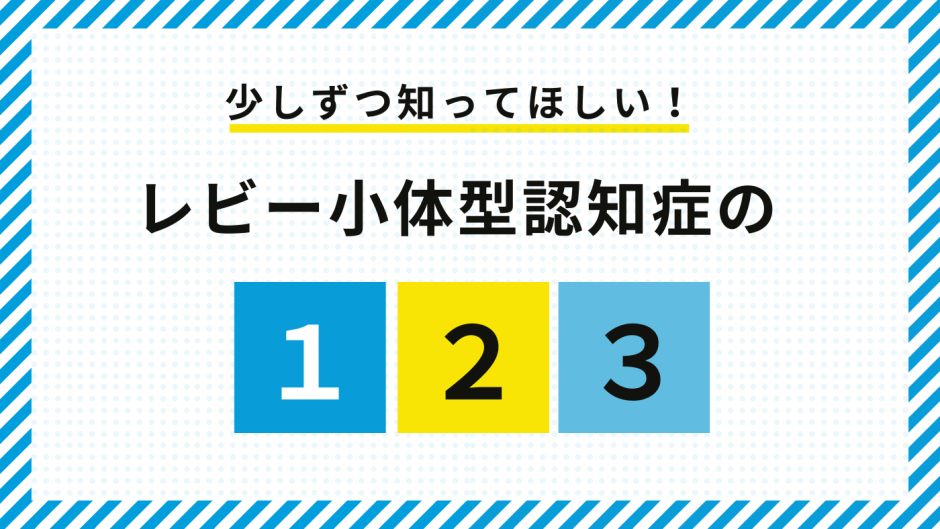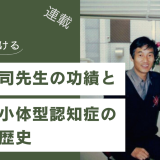レビー小体型認知症の知識は専門家だけのものではありません。世間の人にも知ってほしい。これだけは知ってほしい1・2・3からはじめて、難しい専門のことまで説明していく予定です。(文責:眞鍋雄太、神奈川歯科大学臨床先端医学系認知症医科学分野 認知症・高齢者総合内科 教授)
第2回
— 改めて「認知症」を識る―原因疾患と認知症の関係 —
病態を表す「認知症」。原因となる疾患により脳の認知機能の発動が障害され、社会生活に支障を来した状態、と定義されます。
多くの疾患が「認知症」の原因となるわけですが、レビー小体病が原因となり社会生活に支障を生じ、日常生活を営む上で介助を要する状態になった場合を、レビー小体型認知症(同じレビー小体病でも、手足が振るえる、動きが遅くなる、筋肉の動きが強張るといったパーキンソン症状が先行した場合を特にパーキンソン病と呼称します。パーキンソン病が原因で認知症を呈した場合は、レビー小体型認知症ではなく、認知症を伴うパーキンソン病と呼びます)。

アルツハイマー病が原因で同様の状態になった場合、アルツハイマー病による認知症、すなわちアルツハイマー型認知症と呼称するわけです。〇型認知症の〇の部分に原因疾患名が入ると理解して頂ければ良いかと思います。
第2回の連載はここまでとします。不定期となりますが第3回も掲載予定です。
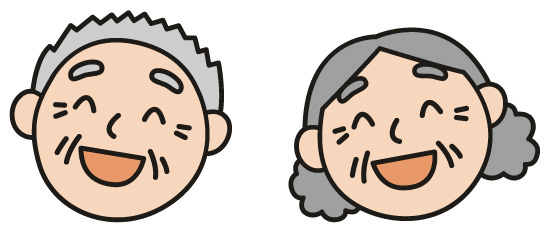
正しい知識を身につけて過度の恐れを持たないようにしましょう(管理人)
 レビー小体型認知症スマイルニュース
レビー小体型認知症スマイルニュース